2021年11月10日・11日の2日間にわたり、LINEのオンライン技術カンファレンス「LINE DEVELOPER DAY 2021」が開催されました。特別連載企画「DEVDAY21 +Interview」では、登壇者たちに発表内容をさらに深堀り、発表では触れられなかった関連の内容や裏話などについてインタビューします。今回の対象セッションは「大規模クライアントアプリ開発チームの生産性を改善した仕組み化の数々」です。
LINEアプリのスタンプに関する機能を担当している、LINE Fukuokaのクライアント開発チームでは、年々増加する機能に応じてチームのサイズも拡大していました。一方でコミュニケーションをボトルネックとする開発遅滞やプラットフォームごとの使用差異、ドキュメント不足などの課題も生じていました。このような状況を改善するための取り組みの内容について、チームでエンジニアリングマネージャーを務める竹下秀則に聞きました
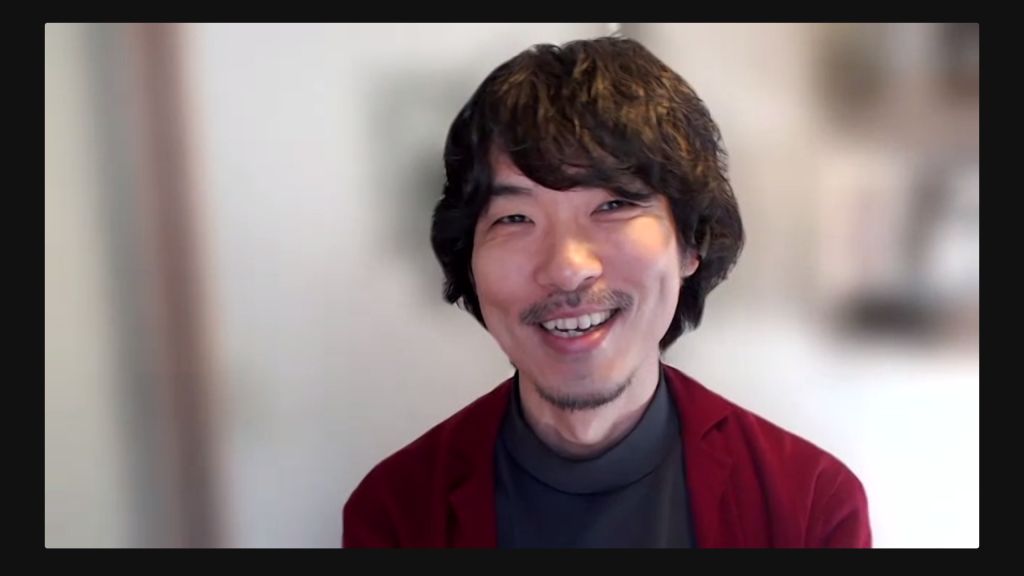
チームとして解決すべき課題の優先順位を見誤った
――まず、チームの概要について教えてください。
竹下:私はLINEの国内第2拠点であるLINE Fukuokaに所属していて、LINEアプリのクライアント開発を担うチームのエンジニアリングマネージャーとして働いています。
所属しているチームにはiOSとAndroidのクライアントエンジニアが所属していて、LINEアプリのスタンプショップなど社内で通称「ショップ」と呼んでいるパートの開発を行っています。このパートが取り扱っているのは、円滑なコミュニケーションのためにユーザーが購入できる、スタンプや絵文字、着せかえ(テーマ)などの機能です。以前は東京オフィスのメンバーで開発を行っていましたが、2017年にLINE Fukuokaが引き継ぎました。
当初のチームメンバーは私を含めて5名でしたが、その後4年ほどで13名にまで拡大しました。
――そのチームで、具体的にどのような課題が生じたのでしょうか。
竹下:主立った課題としては、コードレビューを誰に依頼すればよいかが不明瞭、iOSとAndroidでの実装の差異の負債化、障害の増加、知識の属人化、ドキュメントの整備が不十分といったものなどです。私自身、メンバーの業務知識に偏りがあることや、ドキュメントが不足していることには正直気づいていましたが、自身の忙しさもあって優先度を上げれずに、チームとしての改善方針を検討することもなく後回しにしてしまっていました。
チームとしての様々な課題を抱えながらも大きなサービス障害が発生し、その障害対応に手を取られている間にも他の開発案件を進行させる必要があり、なかなか改善に取り組むことができないというループに陥っていました。これはチームとして解決すべき課題の優先順位を見誤ったことによるマネジメントの失敗で、マネージャーである私自身がチームの成長のボトルネックになっていると思いました。
私が忙しかったのは、他部署とのコンタクトポイントとして、ほとんどの案件の一次コミュニケーションを担っていたからです。関係する部署や人が増えたにもかかわらず、すべてのコンタクトが私に集中したため、コミュニケーションや会議に多くの時間を費やす状態だったのです。
他部署とのコミュニケーションをほかのメンバーに任せられればよかったのですが、メンバーがうまくやれるのかが心配で任せきれずにいました。
実は私のチームメンバーの大半は外国籍で、チームミーティングやチャットでのコミュニケーションはすべて英語で行っています。一方、プランナーなどは他部門の多くは日本人であり、コミュニケーションも日本語がメインとなります。チャットでは翻訳ボットを利用しているほか、会議の際には通訳の方に入ってもらうこともできるのですが、いずれにしても母国語ではない言語でスムーズに意思疎通を図るのは大変です。そのため、関係部署とのやり取りを任せて本当に大丈夫なのかという心配がありました。
しかし、あるときの360度評価において「あなたばかりが前に出てきて、メンバーに仕事を任せようとしないように見える。実はメンバーを信用していないのではないか」というフィードバックを受けました。薄々感じていたことをズバリ指摘されて、これはなんとかするしかないと動き出すことにしました。
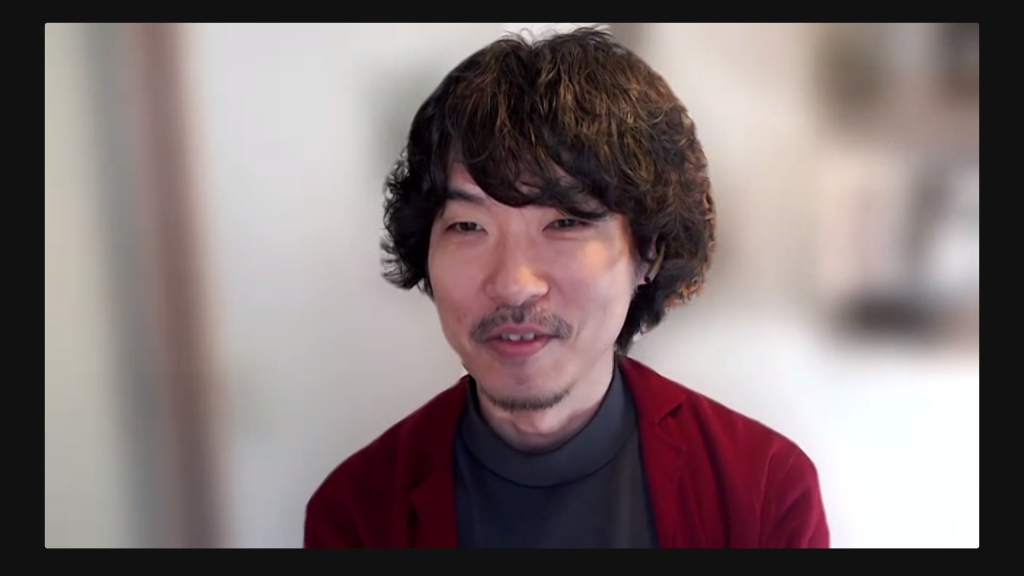
絶対にやると決めて、莫大な量のドキュメントを一気に作成
――関係部署とのコミュニケーションをメンバーに任せるなど、チームの運営方針の変更をチーム内に伝えたときの反応はどうだったのでしょうか。
竹下:最初、チームメンバーとの1対1面談の際に、「最近こういう問題があるから、こういうことを考えるんだけれど」というように話して、ちょっと反応を確かめるところから始めたんですね。そうすると、やっぱり同じような課題を認識していて、「それは全然いいんじゃないですか」とか「チームがよくなりそう」などといったポジティブな反応が得られました。それで手応えを感じ、一気に内容を詰めてチーム全体にプレゼンしました。
振り返ってみると、チームのメンバーも私に余裕がないことに気づいていて、もっと仕事を回してくれればいいのにと思ってた部分があったのかもしれません。それに対して、本当に任せて大丈夫なのかと心配しすぎて自分で抱え込むことになり、周囲から見るとメンバーを信頼していないと捉えられかねない状況になっていたんだなと思います。
方針を決めてチームメンバーに発表したことで、課題をメンバー全員で共有することができて、同じ目線で改善に向けた取り組みを進められたのかなと思っています。
――自分で抱えていた仕事のメンバーへの引き継ぎはどのように進められたのでしょうか。
竹下:こういうケースではこうするなど、やるべきことを文書化し、それをメンバーに渡して実際に対応してもらうようにしました。当然、ドキュメントだけでは対応できないケースも出てくるので、私自身もしっかりチェックしてフォローするような体制を整えています。
実際に大変だったのはドキュメント化の部分です。人に伝わる、わかりやすい文章を、しかも英語で書くのはすごく時間がかかるんですよね。それも、やらなければならないと思いつつ先延ばしにしていた理由の1つなのですが、今回は絶対にやると決めて、相当なボリュームのドキュメントを作成しました。
改革に取り組んだことでチームのメンバーも成長
――チームの生産性に影響はありましたか。
竹下:これまでは、プランナーなどが考えた企画やアイデアを私が受け、そこからディスカッションを行って詳細を詰め、次に開発担当をアサインし、工数などを見積もった上で開発に進むというフローになっていました。
現在は、ディスカッションする時点からコンポーネントリードと呼ばれるエンジニアをアサインして任せるようにしました。これにより、私のところで案件が止まってしまうことがなくなり、スムーズに並列で案件を動かせるようになったことは、生産性の観点でプラスになったと思います。
――チームの雰囲気は変わりましたか。
竹下:チームのメンバーは、私が任せた業務に対して問題なく対応してくれています。また「ここはこうした方がいいんじゃないか」と積極的にアイデアを出してくれるなど、以前よりも自立的に動けている姿が見られているので、この取り組みを進めてよかったと思っています。まさに「案ずるより産むが易し」で、もっと早く取り組めばよかったという感じですね。
――メンバー個々人の成長にもつながっているということですね。
竹下:LINEでは、オーナーシップを持って業務に取り組んでもらうことが求められています。企画当初から携わり、自分の力で関係各所とコミュニケーションしながら作り上げていくことは、そのオーナーシップにつながる部分であり、その意味でエンジニアの成長にもつながる施策になったかと思います。
また、今回の取り組みではレビュープロセスを明確化したため、ほかのエンジニアに対して自分の書いたコードをきちんと説明するといったことも求められるようになりました。これにより、テクニカル面での成長にもつながっていると実感しています。
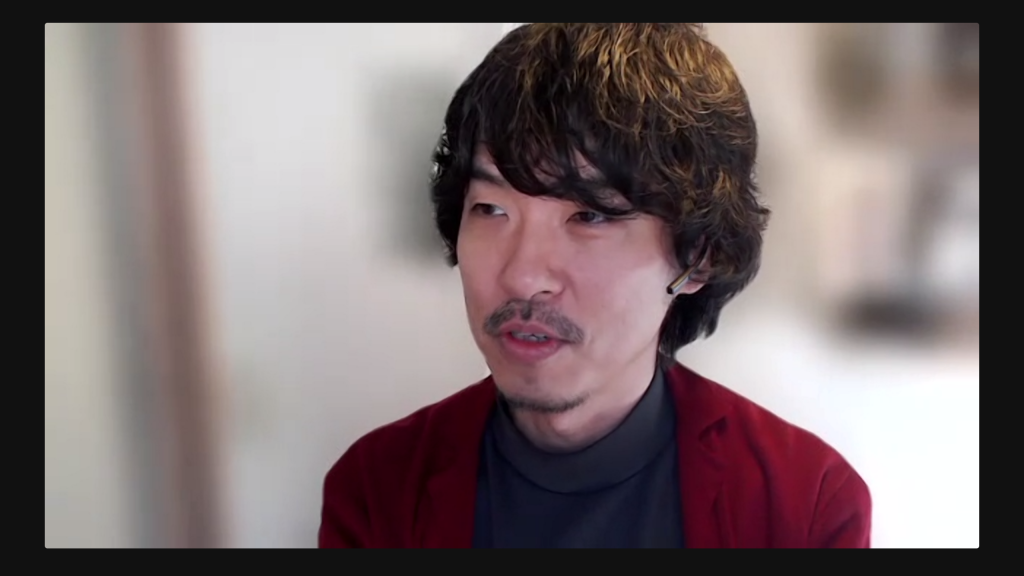
――実際に今回の施策に取り組んだことで、竹下さんの仕事にはどのような変化が生まれましたか。
竹下:マネージャーとしてメンバーを評価することが求められていますが、従来は十分に目配りできていませんでした。しかし現在は、メンバーそれぞれの働きぶりをじっくり観察することに時間を使えるようになっています。
以前は、私がお膳立てして後は任せたという感じの進め方でしたが、現在は最初から仕事を任せられているので、メンバーをしっかり観察して必要であれば手助けするといった形に変わっています。また、チーム拡大のための仕事に取り組めるようになったことも大きな変化で、最近ではエンジニア採用などの業務にも力を入れています。
――セッションでは、考えるための時間として2時間を確保したいが、現状ではまだ難しいというお話がありました。2時間を確保するために、今後どのような取り組みが必要だと考えていますか。
竹下:できる人やポテンシャルがある人、あるいはマネジメントをやってみたいと考えている人、そういった人たちにどんどん仕事を引き継ぎ、マネージャーを育てていく。チームを拡大するためには、そういった取り組みが欠かせないと思います。そうした取り組みを進めつつ、自分が抱えている仕事を任せていくことができれば、将来的には考えるための時間を確保できるかもしれませんね。
裏表ないコミュニケーションで信頼関係を築くことが重要
――まだ取り組みは道半ばという感覚ですか。
竹下:当初考えていた仕組み化を理想通り全て軌道に乗せることがゴールだとしたら、まだ遠いですね。やっと次のステージに進むためのスタート地点に立ったというくらいのイメージです。
山登りで考えると、まだ半分までは行っていない。4合目ぐらいの感覚です。確実によくなっている部分がある一方、まだまだやるべきことはあるなと思っています。
――LINE DEVELOPER DAY 2021での発表に対して反応はありましたか。
竹下:Twitter上で「すごくよかった」とツイートしていただける方がいたほか、社内でもいろんな人たちが見てくれていて、「共感する」、「すごくよかった」といったことがチャットで書かれていて、それをこっそり見つけては感激していました(笑)。
今回のセッションで僕が話したことは、開発組織のマネジメントをされている方が感じる典型的な課題であり、すごく新規性があった話題ではないと思っています。
ただ、今回のセッションでは課題をちゃんと言葉にして伝えたことは意味があったんだろうと考えています。またエンジニアリングマネージャーという役職は徐々に定着し始めていますが、それに関する情報はまだまだ少ないのが現状です。そういった状況での発表だったため、同じような課題を感じている人に刺さる部分はあったのかもしれません。
エンジニアリングマネージャーとして同じように苦労している人たちからすれば、自分が感じている課題が提示されて、それに対する解決策も、そのままどの組織でも適用できるかどうかは別にして提示されているということで、参考にしていただけた部分はあったのではないでしょうか。
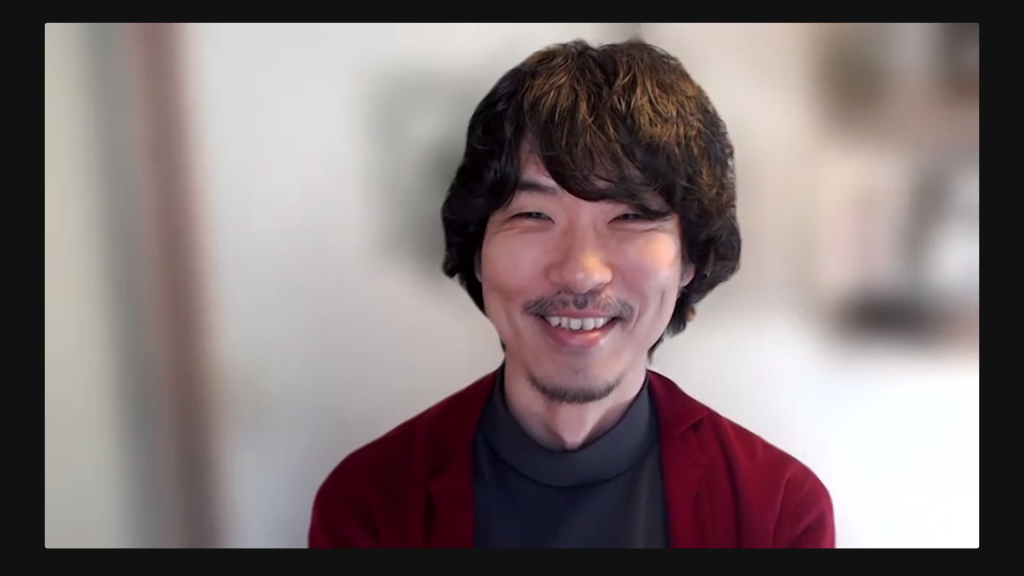
――これからマネージャーになる人、あるいはマネジメントをしていて課題を感じている人にアドバイスはありますか。
竹下:チームをマネジメントするときに発生する課題は、チームのサイズや会社の体制、考え方によってまちまちだと思います。技術とは異なり、これをやっておけばOKだったり、これがベストプラクティスだといったものは、なかなかないのが現実ではないでしょうか。
ただ重要なのは、本質的な問題を見つめることだと思います。チームやチームメンバーをよく観察し、これは将来的に大きな問題になるだろうといった「種」のようなものを見つけたら、手遅れにならないうちに対処することが重要だと思います。
そして、メンバーとの関係はすごく大事だと思います。私自身が心がけていることとしては、普段から裏表なく誠実に接することです。仕事だけでなく、それ以外のことでも何でも話し合えるような信頼関係を作っておかないと、思うように言葉が伝わらないし、何か仕事を頼んだときも前向きに捉えてもらえない可能性があります。
当然ですが、チームメンバーの力を最大限に引き出し、成果を最大化することがマネージャーの役割だと思うので、そのためにもメンバーとの間でしっかり関係性を構築することは重要なステップではないでしょうか。
採用情報
LINE株式会社およびLINE Fukuoka株式会社では一緒に働くエンジニアを募集しています!
今回のインタビューと関連する募集ポジションはこちらです。